著書-歴史と経済に学ぶ経営のための知的財産権
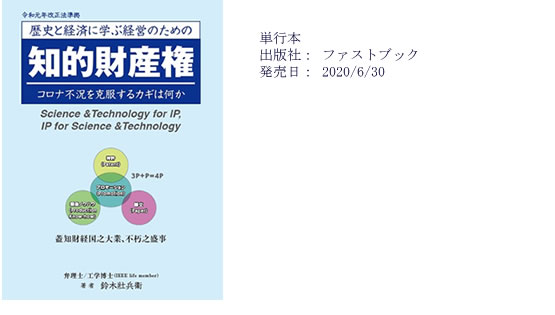
本書の巻頭には、菅直人第94代内閣総理大臣の推薦の辞があるが、本書の第1章では、知的財産権が歴史と経済にどのように関係していたかを説明している。
COVID-19による不況はリーマン不況よりも遙かに深刻で、1929年の世界大恐慌以来の大きな経済危機をもたらすであろうとの予測もある。ウィズコロナ・アフターコロナの時代に適合した新たなイノベーションを創出することと、そのイノベーションを基幹とする実体経済に資金が投入できる社会が必要である。
実体経済と金融経済が乖離している現状を鑑み、経済学的な観点から知的財産権の重要性を知らしめ、グローバルな視野から、我が国の優位性を生かすことを説くものである。
特に、科学技術を創造して、実体経済を活性化し、発展させることが必要であることを力説するもので、科学技術の根幹に位置する知的財産権とは何かを、経営の立場から考えていただこうという趣旨である。
即ち、本書はB5版 全464頁であり、知的財産権が活用される経営を意図した書籍になっている。マーケティングやロジスティックを含めた広い視野から検討する糸口を与える内容にすることにより、従来の知的財産権の本とは異なる視座からの記載をしている。
| 推薦の辞 | 第94代内閣総理大臣 菅直人 | --- 3 | ||
| 前書き | --- 4 | |||
| 第1章 | 知的財産制度の意味と経済学 | --- 10 | ||
| §1.1 | 経済学は、有限な資源を効率的・合理的に配分するための学問 | |||
| §1.2 | アベノミクスを特許のデータから検証する | |||
| §1.3 | 金融機関との連携を可能にするイノベーションと知的財産 | |||
| §1.4 | 第1次産業革命から第3次産業革命へ | |||
| §1.5 | 経済発展と資本の蓄積 | |||
| 第2章 | 知的財産制度の法体系 | --- 39 | ||
| §2.1 | 知的財産とは何か | |||
| §2.2 | 知的財産権の種類と管轄 | |||
| §2.3 | 知的財産法は民法の特別法 | |||
| §2.4 | 民法と特許法とで歴史上どちらが早く制定されたか | |||
| §2.5 | 知的財産権は、不平等条約解消の交渉の武器 | |||
| §2.6 | 権利の分類 | |||
| §2.7 | 民法第709条の枠組みと知的財産権の位置 | |||
| §2.8 | 特許法第103条の過失の推定規定 | |||
| 第3章 | 特許と実用新案 | --- 55 | ||
| §3.1 | 権利主義 | |||
| §3.2 | 特許権の客体的要件 | |||
| §3.3 | 特許権の主体的要件 | |||
| §3.4 | 先願主義と冒認 | |||
| §3.5 | 小発明の保護と活用 | |||
| 第4章 | 特許出願における審査主義 | --- 103 | ||
| §4.1 | 特許発明はサービス可能な真理 | |||
| §4.2 | 特許出願から特許権が発生するまでの手順 | |||
| §4.3 | 補正制限主義 | |||
| §4.4 | 発明の単一性 | |||
| §4.5 | 先行技術を用いた実体審査の内容 | |||
| 第5章 | 特許明細書等の読み方と論文 | --- 138 | ||
| §5.1 | 公有知識と専有知識 | |||
| §5.2 | 科学技術論文と特許出願書類 | |||
| §5.3 | 特許情報検索 | |||
| §5.4 | 無料検索サイト特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) | |||
| 第6章 | 発明の仕方と、特許明細書等の書き方 | --- 169 | ||
| §6.1 | 技術の発達の基本は模倣と改良の連続 | |||
| §6.2 | 理論家の結論したことを信じるな | |||
| §6.3 | 創造とは必然の先見である | |||
| §6.4 | 行動心理学の第1法則 | |||
| §6.5 | 必要が発明の母 | |||
| §6.6 | 起承転結の論理で発想の内容を整理する | |||
| §6.7 | 図面で発明をまとめる | |||
| 第7章 | 意匠登録制度と出願審査 | --- 199 | ||
| §7.1 | 意匠法の目的と我が国の現状 | |||
| §7.2 | 意匠法の保護対象 | |||
| §7.3 | 意匠の審査の手順 | |||
| §7.4 | 意匠の登録要件 | |||
| §7.5 | 関連意匠 | |||
| §7.6 | 組物の意匠 | |||
| §7.7 | 組物の意匠 | |||
| §7.8 | 動的意匠 | |||
| §7.9 | 秘密意匠 | |||
| §7.10 | 分割出願 | |||
| §7.11 | 変更出願 | |||
| 第8章 | ブランドと商標の関係、商標登録制度 | --- 223 | ||
| §8.1 | 商標はブランド要素の一つに過ぎない | |||
| §8.2 | 商標の歴史 | |||
| §8.3 | 我が国の商標法の特色 | |||
| §8.4 | 商標の機能 | |||
| §8.5 | 商標法の形式的保護対象と実質的保護対象 | |||
| §8.6 | 商標法上の商品 | |||
| §8.7 | 商標法上の商標の使用(第2条第3項) | |||
| §8.8 | 商標登録を受けることができる者 | |||
| §8.9 | 一般的・普遍的登録要件(第3条第1項各号) | |||
| §8.10 | 商標の類似 | |||
| §8.11 | 商品・役務の類似 | |||
| §8.12 | 団体商標(第7条) | |||
| §8.13 | 地域団体商標(第7条の2) | |||
| §8.14 | 出願の分割 | |||
| §8.15 | 出願の変更 | |||
| 第9章 | ノウハウの保護と事業収益の達成 | --- 257 | ||
| §9.1 | ノウハウと営業秘密は異なる | |||
| §9.2 | 日本企業の知財マネジメントの問題点 | |||
| §9.3 | 技術のポジショニング分析 | |||
| §9.4 | 迂回の非容易性 | |||
| §9.5 | オープン&クローズ戦略の弁別フロー | |||
| §9.6 | 多値論理によるオープン&クローズ戦略 | |||
| §9.7 | ノウハウ文書の管理 | |||
| §9.8 | ノウハウ文書の作成方法 | |||
| §9.9 | ノウハウを秘匿した場合のデメリット | |||
| 第10章 | その他の知的財産権 | --- 273 | ||
| §10.1 | 著作権法 | |||
| §10.2 | 著作隣接権 | |||
| §10.3 | パブリシティ権 | |||
| §10.4 | 商品化権 | |||
| §10.5 | 不正競争防止法 | |||
| §10.6 | 育成者権 | |||
| §10.7 | 半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |||
| 第11章 | 知的財産権侵害 | --- 324 | ||
| §11.1 | 登録創作権の権利内容 | |||
| §11.2 | 登録創作権に対する侵害 | |||
| §11.3 | 登録創作権の保護範囲 | |||
| §11.4 | 侵害訴訟の審理の概略 | |||
| §11.5 | 登録識別権の侵害 | |||
| §11.6 | 非登録創作権の侵害 | |||
| 第12章 | 国際的知的財産制度 | --- 383 | ||
| §12.1 | コロナ不況を克服するのは技術開発とその頭脳 | |||
| §12.2 | パリ条約 | |||
| §12.3 | 特許協力条約(PCT) | |||
| §12.4 | TRIPs協定 | |||
| §12.5 | 特許法条約(PLT) | |||
| §12.6 | ロカルノ協定 | |||
| §12.7 | ハーグ協定 | |||
| §12.8 | マドリッドプロトコル | |||
| §12.9 | 商標法条約(TLT) | |||
| §12.10 | 商標法に関するシンガポール条約(STLT) | |||
| §12.11 | マドリッド協定(原産地表示) | |||
| §12.12 | リスボン協定 | |||
| §12.13 | ベルヌ条約 | |||
| §12.14 | 万国著作権条約(UCC) | |||
| §12.15 | WIPO著作権条約(WCT) | |||
| §12.16 | ローマ条約 | |||
| §12.17 | UPOV(ユポフ)条約 | |||
| §12.18 | 集積回路についての知的所有権に関する条約(IPIC条約) | |||
| 第13章 | 企業の知的資産経営 | --- 424 | ||
| §13.1 | 機会主義の狡猾さ | |||
| §13.2 | 特許出願は投資の一部である | |||
| §13.3 | 特許の権利化は差別化 | |||
| §13.4 | 特許出願の目的は権利化することではない | |||
| §13.5 | 知的財産経営から知的資産経営へ | |||
| §13.6 | ライセンス契約 | |||
| §13.7 | クラウドファンディング | |||
| 第14章 | 今後の知的財産権 | --- 444 | ||
| §14.1 | サービス業とGAFA | |||
| §14.2 | AIの発達 | |||
| §14.3 | AI以外の人類の課題 | |||
| 第15章 | 特許戦略の補足その他 | --- 453 | ||
| §15.1 | ポートフォリオの形成 | |||
| §15.2 | アインシュタインの沈黙の30月 | |||
| §15.3 | マッカーシーの4Pによる知財権ミックス | |||
| 後書き | --- 461 | |||
| 謝辞 | --- 462 | |||
著書-反骨の風土が独創の力となったのか―明治維新以降の東北地方の科学技術
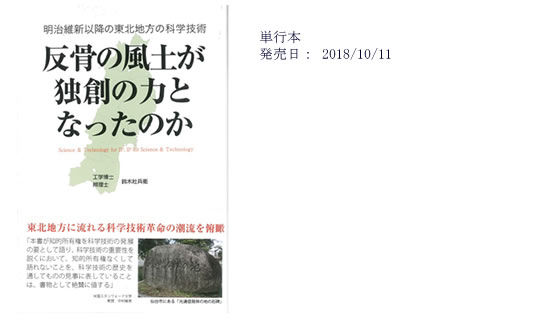
明治時代の初頭において、我が国の科学技術は、英国の物理学の大御所ケルヴィン卿から「世界の工学の中心は日本に移った」と讃えられていた。大正時代においては、アインシュタインが東北大学をライバル視していた。この明治から大正に流れる系譜は昭和の時代に入り、西澤潤一博士(東北大学第17代総長)に引き継がれていたが、西澤先生は平成の時代の独創研究の停滞を嘆いておられた。本書は令和の時代の若手の研究者に奮起を促す書である。
| プロローグ | ||||
| §1 | 日本の特許制度の黎明期の重要人物として仙台藩士玉蟲左太夫がいる | |||
| §2 | 我が国の初代の特許庁長官 は、仙台藩の足軽の養子 | |||
| §3 | 我が国の殖産興業の思想の源流の一つは、会津藩士山本覚馬の管見 | |||
| §4 | 明治7年府県物産表による当時の東北地方の産業の分析 | |||
| §5 | 明治13年には青森県の今野久吉が発明している | |||
| §6 | 東北地方の明治中期の登録特許で一番多いのは福島県 | |||
| §7 | 東北帝国大学本多先生の産学連携 | |||
| §8 | 鯨井先生が八木先生を仙台に送る | |||
| §9 | 東北帝国大学を基軸として日本の科学技術が進歩した | |||
| §10 | 日本のヴァニーヴァー・ブッシュは渡辺先生 | |||
| §11 | 特許収入を基礎とした財団法人半導体研究振興会が仙台に | |||
| §12 | 西澤先生の発明が第2次産業革命の完結へのキーデバイス | |||
| §13 | 第3次産業革命は仙台で発生した | |||
| エピローグ | ||||
著書-日米欧中韓共通出願様式時代 特許明細書等の書き方 プロフェショナル・アマチュアのための教本 [単行本]
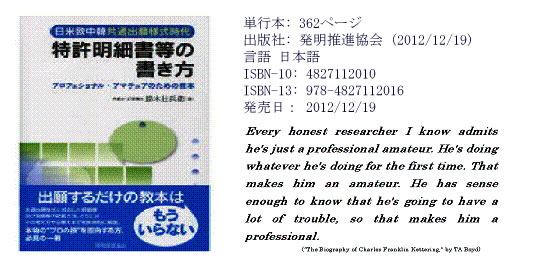
本書は単なる「特許明細書等の書き方」を表面的に説明する技術書ではない。研究開発のスピリットとしての「プロフェッショナル・アマチュア」を説いたのは、チャールズ・フランクリン・ケタリング(Charles Franklin Kettering)である(Boyd, T. A. “Professional Amateur: The Biography of Charles Franklin Kettering”. E. P. Dutton & Co, (1957))。
ケタリングの名言に従たがえば、「初めて特許明細書等を手掛ける事に付いては、あくまでもアマチュアであるが、特許の権利化と事業への活用のためには多くの困難を乗り越えなければならぬことをよく承知しているという意味でプロフェッショナルでなければならない」ということになろう。27年間GMの研究所を率いたケタリングは、高圧点火システムの特許(1910年)の他、米国で300以上の特許を取得している。
本書は2010年に刊行した「日米欧三極共通出願時代の特許クレームドラフティング」の姉妹編である。「日米欧三極共通出願時代の特許クレームドラフティング」では【特許請求の範囲】記載について詳細に説明したが、本書では、【特許請求の範囲】以外の【明細書】及び【図面】が主なる対象として、従来の古い明細書等の書き方を脱却した、新しい書き方を説明する。
例えば、第3章にデカルトの要素還元主義の話がでてくるように、本書では、なぜそのように書くのかの理由付けを、歴史的経緯や哲学的背景等を踏まえて、より掘り下げてプロフェッショナルな観点から説明している。現在、特許の専門家のための特許明細書等の書き方の本は多数出版されており、一方、特許の非専門家のアマチュアのための特許明細書等の書き方の本も多数ある。
しかし、残念ながら、多くのアマチュアのための特許出願の教本は、特許出願をするための安易な教本であって、特許庁の審査に合格でき、更に、権利行使が可能なレベルのプロフェッショナルな目線でのテキストがない。現在の教本は、明細書の書き方は、どのようにすべきか、或いは、どのような明細書が品質の高い明細書であるか、ということまでは指導していない。
なぜそのように特許明細書等を書くのかの掘り下げたプロフェッショナルなレベルでの理解がなければ、どのような明細書が品質の高い明細書であるかは理解できない。ただマニュアルに従った、応用力のない表面的な書き方では、ケタリングのスピリットに悖ることとなる。なお、特許の専門家のための特許明細書等の書き方の本の場合も、専門的事項については詳しい説明があるが、その前提となる基本的事項については、なぜそのように書くのかの理由付けを、深く掘り下げていないのが現状である。
したがって、従来の「特許明細書等の書き方」の本は、所謂、実用書としての表面的な書き方になってしまっているというのが実情である。本書は、10年以上明細書を書かれている経験者であっても、「おっ!」と思われる事項や、ご批判を含めて何らかの議論の参考になりうる内容の記載があるものと考えている。
特に、アマチュアが書いた明細書で良く見られる不備は、明細書中の【発明を実施するための形態】の欄の説明が非常に薄いことである。本書は、特許の非専門家のアマチュアであっても、弁理士や弁理士を補佐する特許事務所の技術者レベルの品質を実現可能な、則ち、プロレベルの明細書及び図面等の記載方法を、長く特許事務所の内部において指導してきた経験を踏まえて、具体的に説明する。
中小企業は日本の全企業の99.7%を占めるが、その出願件数は年間3万件程度であり、これは、日本の全出願件数の1割にも満たない。弁理士を代理人としないで、特許のアマチュアである中小企業の経営者等の特許出願人が直接、特許庁に手続して、特許出願することは、特許出願という手続だけに着目すれば、かなり簡単に可能である。元特許庁長官の荒井寿光先生(現東京中小企業投資育成株式会社社長)は、中小企業の経営者らに、15000円の印紙代のみで、直接、特許庁に手続して特許出願する方法を勧められている。
しかし、特許は出願すれば権利が発生するのではなく、特許庁の審査官の審査を受けて、審査に合格した特許出願のみが、特許査定されて、登録される。が、弁理士が記載したものを含めて、実に、特許出願された全件数の内、約75%程度は登録されない。
又、特許出願人が、特許庁に直接手続しない場合であっても、本書を参考にして、ある程度完成度の高い特許提案書又は発明説明書を作成して弁理士に依頼すれば、結果として中小企業等の特許出願の経費の削減が期待できる。ある程度完成度の高い特許提案書や発明説明書を弁理士に提出すれば、弁理士の手間が省略可能となるからである。
「特許明細書等の書き方」は基本的に自由であるが、書類には作成者の心が反映される。本書は、特許明細書等をなぜそのように記載するのかという、書き方の背景にある考え方や法律的根拠を説明し、更に、特許を事業に活用するという事業優先の観点を紹介する。事業優先の戦略に沿った特許出願のしかたは如何にすべきか、或いは、事業優先の戦略の背景にある考え方や法律的根拠を理解しなければ、特許出願は意味のないものとなる。
本書は、企業の知的財産部員や弁理士等の特許の専門家(プロ)と同程度の技量を指向した、中小企業の経営者や個人等の特許に関するアマチュアを主に対象としているが、未だプロとしての技量が未完成な若い弁理士の方や弁理士を補佐する技術者や、一応の経験を積まれた方にも何らかの参考になるものと考えている。
| 第1章 | 出願するだけなら、この本は読まなくてもよい | |||
| §1.1 | 技術の文書化 | |||
| §1.2 | 出願公開と特許庁での審査 | |||
| §1.3 | 拒絶理由通知の内容 | |||
| §1.4 | 記載不備の拒絶理由通知の内容 | |||
| §1.5 | 技術文献作成技法は日本語作成技法を基礎とする | |||
| §1.6 | 互いに極性が反対となる、2種類の読者を意識する | |||
| §1.7 | 日本語作成技法の具体例 | |||
| §1.8 | 技術文献作成技法の具体例 | |||
| §1.9 | 法律文書では、安易に括弧書きの表現や下線を用いない | |||
| 第2章 | 補正制限主義と特許出願書類の役割 | |||
| §2.1 | 審査官から拒絶されたらどうするか | |||
| §2.2 | 手続補正書において、新規事項を追加できない | |||
| §2.3 | 新規事項とは何か | |||
| §2.4 | 「最初の拒絶理由」と「最後の拒絶理由」 | |||
| §2.5 | 出願の分割と変更 | |||
| §2.6 | 衡平の原則と、特許出願の目的 | |||
| §2.7 | 特許出願書類の果たす役割 | |||
| §2.8 | 均等論 | |||
| §2.9 | 完全な特許出願書類 | |||
| §2.10 | 発明の本質が分かりやすい特許出願書類 | |||
| §2.11 | 出願経過禁反言(エストッペル)の法則 | |||
| §2.12 | 明細書の推敲編集 | |||
| §2.13 | 特許出願書類は生き物 | |||
| 第3章 | 発明の目的、構成及び効果 | |||
| §3.1 | 項分け記載をどのように整理するのか | |||
| §3.2 | 項分け記載と、起承転結の論理の整合 | |||
| §3.3 | 【発明が解決しようとする課題】は不安定 | |||
| §3.4 | 起承転結の論理の整合から見える余分な限定事項 | |||
| §3.5 | 製造物責任法(PL法)に注意: | |||
| 第4章 | サポート要件 | |||
| §4.1 | 発明完成過程 | |||
| §4.2 | 特許発明の技術的範囲と特許法第36条第4項と第6項 | |||
| §4.3 | 選択発明と穴あき説 | |||
| §4.4 | 発明が「明細書に記載したもの」であるか | |||
| §4.5 | 【課題を解決するための手段】の欄に請求項のコピーをしない | |||
| §4.6 | 【発明を実施するための形態】の欄と請求項の記載 | |||
| §4.7 | 米国流の【課題を解決するための手段】の欄の記載法 | |||
| §4.8 | 米国流と欧州流の書き方は互いに調和しない | |||
| §4.9 | 包括的記載を明細書のどこかに記載 | |||
| 第5章 | 「発明を実施するための形態」とは | |||
| §5.1 | 実施形態と実施例 | |||
| §5.2 | 各実施形態の効果は、どこに、どのように記載すべきか | |||
| §5.3 | 各実施形態の内部のストーリ構成は項目毎に分けて | |||
| §5.4 | 発明の特徴は方法にしかないのか? | |||
| §5.5 | 項目毎の分類記載をしていないと方法の説明の流れが停滞する | |||
| §5.6 | 「実施例」とは | |||
| §5.7 | ゼノンの逆理 | |||
| §5.8 | 内容の異なった実施形態 | |||
| §5.9 | 機能的表現の請求項と、実施例限定解釈への対策 | |||
| §5.10 | 一部でも数値範囲が重複していたら新規性がない | |||
| §5.11 | 拒絶理由応答への種々の布石 | |||
| §5.12 | 特許請求の範囲と明細書は、互いに異なる文書術で記載 | |||
| §5.13 | 各実施形態の冒頭部の説明と、それに続くストーリ構成 | |||
| §5.14 | 読者の立場で、読者に親切なインデックスを用いる | |||
| §5.15 | 「項分け記載」と冗長表現 | |||
| §5.16 | 【発明を実施するための形態】の欄の文章作成技術 | |||
| 第6章 | 図面の表現 | |||
| §6.1 | 製図は技師の右手である | |||
| §6.2 | 断面の切り口面には、必ずハッチングをいれる | |||
| §6.3 | 図面のみの記載を単独で補正の根拠に使うのは可能か? | |||
| §6.4 | 明細書中の文章の記載と図面中の部材の符号 | |||
| §6.5 | 部材の符号はどのようにして図面に付すのか | |||
| §6.6 | 図面を順に並べれば、特許出願書類作成のストーリが構築される | |||
| §6.7 | 各実施形態に対応するように整理した図面 | |||
| §6.8 | 発明のカテゴリーに対応した整理された図面 | |||
| §6.9 | 請求項対応図 | |||
| §6.10 | 本発明の特徴をどのように強調するか | |||
| §6.11 | 平面図と断面図 | |||
| §6.12 | 簡潔かつ明瞭で、理解しやすい図面か | |||
| §6.13 | 自然法則を適切に用いた図面か(技術的な正確性) | |||
| §6.14 | 電気回路の表現 | |||
| 第7章 | 技術的ブラッシュアップ | |||
| §7.1 | 実験結果や、当初考案したアイデアをそのまま特許出願しない | |||
| §7.2 | 消極的ブラッシュアップ | |||
| §7.3 | 思想の抽象化レベルの広がり | |||
| §7.4 | 発明のカテゴリーの広がり | |||
| §7.5 | 異なった視点からの発明 | |||
| §7.6 | 上位概念化の落とし穴 | |||
| §7.7 | 積極的ブラッシュアップ | |||
| 第8章 | ストーリ構成と文章の美しさ | |||
| §8.1 | 各図面に記載された技術内容を、どの順番でスケッチするのか | |||
| §8.2 | 物の説明なのか、方法(製造方法)の説明なのか | |||
| §8.3 | 説明のメリハリとインパクト | |||
| §8.4 | 各実施形態の説明は、発明の名称を意識する | |||
| §8.5 | 短文化と一文一意の原則 | |||
| §8.6 | 代名詞は使用しない | |||
| §8.7 | 用語の選択と統一 | |||
| §8.8 | 日本語主義 | |||
| §8.9 | 技術的に正確な日本語 | |||
| §8.10 | 段落の割り振りと段落間の接続 | |||
| §8.11 | 情報量が多く且つ簡潔な明細書を迅速に仕上げる | |||
| §8.12 | 特許慣用語は避け、できるだけ平易な用語を用いる | |||
| §8.13 | 定量的表現と数値限定の客観性 | |||
| §8.14 | 美しい文章 | |||
| §8.15 | 電気回路の説明はどのようにするのか | |||
| 第9章 | 科学技術論文と特許出願書類 | |||
| §9.1 | 特許出願書類の構成と科学技術論文の記載内容は類似している | |||
| §9.2 | 科学技術論文のタイトルと明細書の【発明の名称】 | |||
| §9.3 | 科学技術論文のアブストラクトと要約書 | |||
| §9.4 | 科学技術論文の「第1章: 緒言」と明細書の【技術分野】、【背景技術】及び 【発明の概要】 |
|||
| §9.5 | 科学技術論文の「第2章 △△について」と明細書の【背景技術】及び【発明が 解決しようとする課題】 |
|||
| §9.6 | 科学技術論文の「第3章 ○○の理論的検討」と明細書の【発明を実施するための 形態】 |
|||
| §9.7 | 科学技術論文の「第4章 実験と考察」と明細書の【発明を実施するための形態】 | |||
| §9.8 | 科学技術論文の「第5章 結言」と、【特許請求の範囲】及び【課題を解決する ための 手段】 |
|||
| 第10章 | 特許請求の範囲の記載は弁理士に相談 | |||
| §10.1 | 特許請求の範囲の記載にあまり時間を使わない | |||
| §10.2 | 順次列挙形式と個条書式: | |||
| §10.3 | デカルトの要素還元主義 | |||
| §10.4 | 構成要件相互の関係を、「該」と「前記」だけで規定する論理 | |||
| §10.5 | 請求項に「所定の」は、用いない | |||
| §10.6 | 文字数の少ない請求項が良い請求項である | |||
| §10.7 | デカルトの第4準則が重要: | |||
| 付録1 | ガリレオ式明細書の書き方 | |||
| 付録2 | 論文記載型明細書の書き方 | |||
| 付録3 | 出願書類チェック表 | |||
| 付録4 | 明細書の参考例 | |||
著書-日米欧三極共通出願時代の特許クレームドラフティング
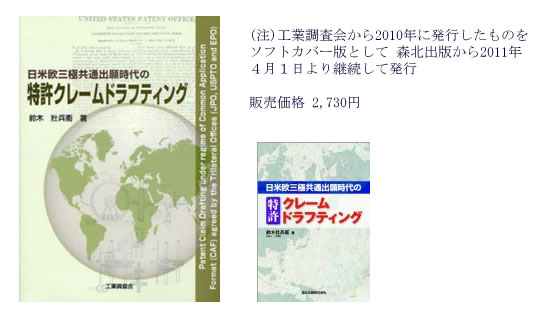
中小企業・ベンチャー企業等の発明者が直接特許庁に手続して特許出願をすることは可能である。その場合、一番苦労するのは特許請求の範囲の記載、即ち、「クレームドラフティング」であろう。特許請求の範囲の記載は特に権利内容を確定する権利書としての性格を有するものである。明細書の方は、学術論文の記載と共通する面が多いので、少し慣れれば、一応の形式は整う。しかしながら、大学教授でも、クレームドラフティングがきちんとできる方は少ない。日本国特許庁では2009年1月1日から日米欧三極共通出願様式への移行を行った。本書は、このような日米欧三極特許庁の動向を踏まえ、従来の日本型仕様から、欧米式に変えるためのクレームドラフティングの文章術などを、より実務に即した観点から、具体的に説明する。 本書は、特許に馴染みの薄い学生、新しい製品を世に出そうとされている経営者や起業家、経験の浅い大学や企業の知財部の方、若い弁理士やその補助者の方等が、クレームドラフティングを勉強するのに、好適な特許の入門書である。
| 第1章 | 日本出願におけるクレームの骨格構造 | 頁 | ||
| 1.01 | クレームドラフティングとは | 12 | ||
| 1.02 | 歴史的には、クレームの法律的規定は米国の1836年法から | 13 | ||
| 1.03 | 特許における世界的ハーモナイゼーションへの方向性 | 16 | ||
| 1.04 | 日米欧三極共通出願様式による利益 | 18 | ||
| 1.05 | 米国特許のクレームも、1836年法当時は、単なるまとめ | 19 | ||
| 1.06 | 米国特許のクレームの骨格構造と日本出願 | 21 | ||
| 1.07 | 日本出願では欧州特許条約(EPC)型のクレームはなるべく使わない | 25 | ||
| 1.08 | 米国型と欧州型はハーモナイズできない | 28 | ||
| 第2章 | 「物」の発明のクレームの文章術 | |||
| 2.01 | 基本的注意点 | 34 | ||
| (1) | 一語一意の原則 | 35 | ||
| (2) | 発明の特徴の抽出と余分な限定 | 38 | ||
| (3) | 「発明特定事項」を記載する | 40 | ||
| (4) | 「物」は互いに異なる部品(構成要件)から成り立っている | 43 | ||
| (5) | 階層的に整理した表現 | 47 | ||
| (6) | クレームは、明確且つ簡潔に | 48 | ||
| (7) | クレームは、米国の「個条書式(組合せクレーム)」が基本 | 49 | ||
| (8) | 「個条書式」の中に「と書き」を使わない | 52 | ||
| (9) | 「おいて書きプレアンブル」が必要な場合は限られる | 53 | ||
| (10) | 構成要件を2重に定義しない(一部材一名称の原則) | 54 | ||
| (11) | 構成要件が少ないほど良いクレーム | 55 | ||
| (12) | クレームとは、構成要件相互の関係を規定する論理である | 57 | ||
| (13) | 原則、クレームに論理和(OR)の関係を用いてはならない | 60 | ||
| (14) | 接続関係だけでは、構成要件相互の関係を規定できない場合もある | 62 | ||
| (15) | 「前記」が省略出来る場合がある | 64 | ||
| (16) | 細部の構成要件(発明特定事項)の相互の関係も考慮する | 65 | ||
| (17) | 構成要件(発明特定事項)をどの順番で記載するのか | 66 | ||
| (18) | 順に接続関係を追って書くのが容易 | 67 | ||
| (19) | 「個条書式」の形式で記載するなら、「突然出現要素」がないように | 69 | ||
| (20) | 順に信号の流れを追って書くのが容易 | 70 | ||
| (21) | 構成要件(発明特定事項)の名称も順番に | 70 | ||
| (22) | クレームにおける「一文一意の原則」 | 72 | ||
| (23) | クレームにおける「かかり結び」 | 73 | ||
| (24) | ハードウェア資源の構造なのか、情報の内容なのか | 76 | ||
| (25) | 部材に別の名前を付けただけでは構造を限定したことにはならない | 78 | ||
| (26) | 部材の名称と、その機能を表現する言葉を合わせる | 79 | ||
| (27) | フェアバイ文節(whereby clause)の使用は避ける | 80 | ||
| (28) | 「物の構造を記載する」とは、本文に「物」としての部材を列記 | 81 | ||
| (29) | クレームドラフティングにおける文章技術 | 82 | ||
| 2.02 | 従属クレームの書き方 | 83 | ||
| (1) | 従属クレームの基本 | 83 | ||
| (2) | クレームの階層構造を整理 | 86 | ||
| (3) | 余分な限定をしない | 88 | ||
| (4) | 従属クレームの表現形式 | 89 | ||
| (5) | 複雑な従属クレーム | 90 | ||
| (6) | 構成として論理的矛盾がないか | 92 | ||
| (7) | 従属関係にある親と子で、技術的な自己矛盾がないか | 93 | ||
| (8) | 「無意味な従属クレーム」になっていないか | 93 | ||
| (9) | 従属クレームとその従属すべき親クレームとの関係 | 96 | ||
| (10) | カテゴリーの異なる従属クレームは避ける | 100 | ||
| 2.03 | プロダクト・バイ・プロセスのクレームについて | 101 | ||
| (1) | 「物」の発明は、「構造としてその物が一義的に特定出来るか?」が重要 | 101 | ||
| (2) | 具体例 | 103 | ||
| (3) | 用語を選ぶ | 105 | ||
| 2.04 | その物の図が、描けるか | 105 | ||
| 2.05 | クレームは、なるべく短く | 110 | ||
| 2.06 | 「物の発明」のクレームと「物の使用方法の発明」又は 「物の製造方法の発明」のクレームとは互いに投影される |
112 | ||
| (1) | コンピュータ・ソフトウエア関連発明における「物」の発明のクレーム | 112 | ||
| (2) | コンピュータ・ソフトウエア関連発明以外でも同様である | 114 | ||
| 2.07 | 時間とともに変化するものを「物の発明」の構成要件としない | 116 | ||
| 2.08 | クレームは対称性を有する | 116 | ||
| 2.09 | 機能的記載のクレーム | 118 | ||
| 2.10 | 「外延」又は「内包」が明確であること | 126 | ||
| 2.11 | ひとまとまりの技術的思想が把握できるか | 127 | ||
| 2.12 | 自然法則を適切に用い、技術的に正確か | 128 | ||
| 2.13 | 特殊な形式のクレーム | 129 | ||
| 2.14 | すべての実施の形態の上位概念となるクレーム | 130 | ||
| 2.15 | 用語の上位概念化 | 132 | ||
| 2.16 | 上位概念化に伴う落とし穴 | 133 | ||
| 2.17 | 複数のカテゴリーがある場合 | 135 | ||
| 2.18 | どの観点から発明を認識しているか | 136 | ||
| 2.19 | 権利行使相手の実施行為に合っているか | 139 | ||
| 2.20 | 「メインクレームに数値限定を使わない」を原則とすべし | 140 | ||
| 2.21 | クレームに数式を用いることの是非 | 141 | ||
| 2.22 | 条件分岐の一方のみの記載は不明瞭 | 142 | ||
| 第3章 | 「方法」の発明のクレームの文章術 | |||
| 3.01 | 基本構造 | 146 | ||
| 3.02 | 方法の発明は、「箇条書式」の形式で記載 | 147 | ||
| 3.03 | 「動詞結合流し書き」の形式と、112条第6パラグラフの問題 | 149 | ||
| 3.04 | 方法の発明における構成要件(発明特定事項)の相互の関係 | 150 | ||
| 3.05 | クレームに効果や目的を記載しない | 152 | ||
| 3.06 | 安易に時系列の順序を規定しない | 153 | ||
| 3.07 | ステップ、段階、工程に余計な修飾をする必要はない | 155 | ||
| 3.08 | 方法のクレームでは3W1H又は2W1Hの記載 | 157 | ||
| 3.09 | 製造方法のクレームでは4W1H又は3W1Hの記載 | 158 | ||
| 3.10 | 部材名に時系列的変化における論理的矛盾がないか | 158 | ||
| 3.11 | クレームは対称性を有する | 162 | ||
| 3.12 | 閉じたクレーム | 163 | ||
| 3.13 | 従属クレームの書き方 | 164 | ||
| (1) | 基本的事項 | 164 | ||
| (2) | クレームの階層構造を整理 | 165 | ||
| (3) | 無用な限定をしない | 167 | ||
| (4) | 「方法の発明」のクレームの方が、従属関係にある親と子での矛盾が発生しがち | 168 | ||
| 3.14 | 方法のクレームは方法らしく | 170 | ||
| 3.15 | 「物の発明」との投影(写像)関係 | 172 | ||
| 3.16 | カテゴリーが異なる場合の投影(写像)関係 | 173 | ||
| 3.17 | 「物の製造方法」のクレームから、その目的物の構造が分かるか | 177 | ||
| 3.18 | 対応する時系列を説明する図面があるか | 178 | ||
| 3.19 | 原則、クレームに論理和(OR)の関係を用いてはならない | 179 | ||
| 3.2 | プレアンブルと本文との表現を一致させる | 179 | ||
| 3.21 | 「かかり結び」の関係を明確にするにはステップを細分化 | 181 | ||
| 3.22 | 権利行使相手の実施行為に合っているか | 182 | ||
| 3.23 | 方法の発明のクレームが先か、物の発明のクレームが先か | 183 | ||
| 第4章 | 日本語と数値限定 | |||
| 4.01 | 特許慣用語は避け、できるだけ平易な用語を用いる | 186 | ||
| 4.02 | 日本語主義 | 187 | ||
| 4.03 | 英単語の頭字語にはフルスペルを併記 | 188 | ||
| 4.04 | 明確な用語を用いる | 190 | ||
| (1) | 相対的な程度を表す形容詞は、基準と比較する | 190 | ||
| (2) | 形容動詞及び形容動詞の連体形にも注意が必要 | 191 | ||
| (3) | 「約(about)」は米国で使える(発明の外延と内包を不明確にする副詞等) | 192 | ||
| (4) | 発明の外延と内包を不明確にする接続詞 | 95 | ||
| (5) | 技術内容を十分検討した日本語を選ぶ | 196 | ||
| 4.05 | 冗長な用語は無駄な限定 | 198 | ||
| (1) | クレームに「所定の」は、用いない | 199 | ||
| (2) | 「少なくとも一部又は全部」は、何を意味しているのか | 200 | ||
| (3) | 安易な上位概念化をしない | 200 | ||
| (4) | 常に基板や基体が必要なのではない | 200 | ||
| 4.06 | 否定的表現(ネガティブ表現)は避ける | 201 | ||
| 4.07 | 除くクレーム | 202 | ||
| 4.08 | 材料名なのか部材名なのか | 203 | ||
| 4.09 | 学術用語が基本 | 204 | ||
| 4.10 | 図面の参照やオムニバスクレーム | 205 | ||
| 4.11 | 数値限定 | 206 | ||
| 第5章 | 強く、広い権利保護 | |||
| 5.01 | 明細書のサポート要件(法36条第6項第1号) | 212 | ||
| 5.02 | 技術的思想の抽出と検討 | 219 | ||
| (1) | 一発明多出願の原則(第1の軸) | 219 | ||
| (2) | 第2の軸:思想の抽象化レベルの広がり | 221 | ||
| (3) | 第3の軸:発明のカテゴリーの広がり | 225 | ||
| (4) | 第4の軸:異なった視点 | 228 | ||
| 5.03 | 発明の特徴の抽出と整理と展開 | 231 | ||
| (1) | クレームドラフティングで一番重要なもの | 231 | ||
| (2) | 発明の特徴の抽出 | 232 | ||
| (3) | 発明の特徴の整理 | 232 | ||
| (4) | 発明の特徴の展開 | 233 | ||
| (5) | EPCにおける進歩性の判断も起承転結 | 235 | ||
| 5.04 | 動的クレームドラフティング | 236 | ||
| 5.05 | ポリバレント(polyvalent)なクレームドラフティング | 240 | ||
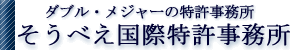
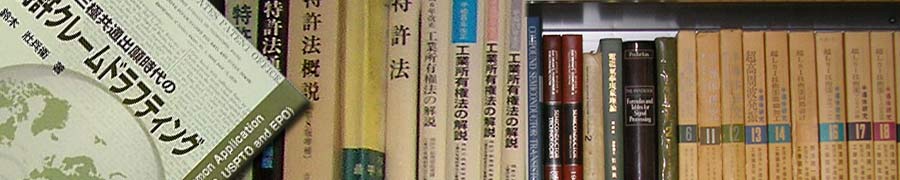

 日米欧中韓共通出願様式時代 特許明細書等の書き方 プロフェショナル・アマチュアのための教本 [単行本]
日米欧中韓共通出願様式時代 特許明細書等の書き方 プロフェショナル・アマチュアのための教本 [単行本] 反骨の風土が独創の力となったのか―明治維新以降の東北地方の科学技術 [単行本]
反骨の風土が独創の力となったのか―明治維新以降の東北地方の科学技術 [単行本] 新刊「歴史と経済に学ぶ経営のための知的財産権」
新刊「歴史と経済に学ぶ経営のための知的財産権」